【医師監修】子どものおやつに“添加物”は危険?安全?アセスルファムK・人工甘味料の本当の安全性を医学的に解説
この記事は医師による医学的監修を含みます。
国内外の論文・公的評価報告(WHO, EFSA, 厚労省 など)に基づき、一般向けに分かりやすく整理しています。
「子どものおやつ、これって大丈夫なの?」
原材料欄にずらりと並ぶ「カタカナ成分」。
アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム…。
“なんとなく身体に悪そう”という印象を持つ方は少なくありません。
この記事では、これらの添加物が実際にどこまでリスクがあるのか、
またどのくらいの量なら安心してよいのかを、最新の医学データをもとに解説します。
1. 添加物=即危険、ではない理由
まず大前提として、食品添加物はすべて「安全性評価」を受けてから使用が認可されます。
日本では厚生労働省、国際的にはFAO/WHO合同食品添加物専門家委員会(JECFA)が評価を担当しています。
安全性評価では、動物実験などで「この量までは影響が出なかった」という量(NOAEL)を求め、
そこから100倍以上の安全係数を掛けて、1日摂取許容量(ADI)を設定します。
1日摂取許容量(ADI)は以下の通りです:
- アセスルファムK:15 mg/kg体重/日(JECFA基準)
- スクラロース:5 mg/kg体重/日
- アスパルテーム:40 mg/kg体重/日
体重20kgの子どもであれば、アセスルファムKを1日あたり300mgまでが“安全域”とされます。
市販のジュース1本(500ml)に含まれる量は多くても40〜60mg前後。
つまり日常的な摂取量ではADIを大きく下回ることがわかります。
2. 「危険」と言われる根拠は何か?

(1)発がんリスク
2022年のフランスの大規模コホート研究(NutriNet-Santé, PLoS Medicine)では、
人工甘味料を多く摂取する人で全体的ながんリスクが13%高いという結果が出ました。
特にアスパルテームとアセスルファムKで強い相関が見られました。
ただしこの研究は観察研究(関連性の調査)であり、因果関係を証明したものではありません。
食生活・肥満・喫煙などの交絡因子が完全には除外されていないため、
「人工甘味料が直接がんを起こす」とは言い切れません。
(2)代謝・糖代謝への影響
人工甘味料は血糖値を直接上げませんが、脳の甘味受容体や腸内細菌叢に影響する可能性が報告されています。
特にスクラロースは腸内細菌の多様性を減らし、インスリン反応性に影響するという動物実験結果があります。
(Suez J et al., Cell 2014)
ただしヒトでの明確な悪影響は一貫しておらず、
「甘い味を日常的に摂取することで甘味嗜好が強化される」
という行動的影響のほうが現実的リスクと考えられています。
(3)心血管疾患との関連
2023年のBMJ報告では、アスパルテームやアセスルファムKの摂取が
心血管疾患リスクの上昇と関連したとされています。
ただし、こちらも因果を証明するものではなく、
肥満傾向や甘味嗜好といった背景要因の影響が強いと考えられます。
3. 「まったく問題ない」とも言えない理由
毒性学的には「一定量以下なら安全」ですが、
臨床的には次の3つの不確実性が残ります。
- ① 複数の添加物を同時に摂る「カクテル効果」
- ② 成長期の子どもは代謝酵素が未熟で感受性が高い
- ③ 長期的影響(10年以上)を検証する研究は限られている
特に小児では、体重あたりの摂取量が多くなりやすく、
同じ食習慣でも「過剰」になりやすい傾向があります。
また、アスパルテームなどはPKU(フェニルケトン尿症)では禁忌です。
4. 医師が考える“現実的な安心ライン”

完全に避ける必要はありませんが、
次のような目安であれば健康上のリスクは極めて低いと考えられます。
| 食品カテゴリ | 摂取頻度の目安 | コメント |
|---|---|---|
| ゼロカロリー飲料 | 週1〜2本まで | 常飲すると甘味依存を助長。特別な日のご褒美に。 |
| 人工甘味料入りガム・キャンディ | 1日1〜2個程度 | 虫歯予防目的のキシリトールは例外的にOK。 |
| 無糖ヨーグルトや手作りおやつ | 制限なし | 自然由来の甘味(はちみつ・果物)で代替可。 |
「完全排除」ではなく、摂取頻度と量を“日常では減らす”というのが現実的なスタンスです。
5. 「無添加=安全」でもない理由
一方で、「無添加」「オーガニック」をうたう商品にも注意が必要です。
天然由来の成分でも、摂りすぎればアレルギー反応や過敏症を起こすことがあります。
「科学的根拠のない“無添加神話”」に流されず、科学的リテラシーで判断する姿勢が大切です。
6. まとめ:子どもを守るための「現実的な選び方」
- 人工甘味料は通常摂取量では明確な害は確認されていない
- ただし、過剰摂取・長期摂取・成長期の子どもでは注意が必要
- 避けるよりも、摂る頻度と量を調整するのが最も合理的
- 親が成分表示を読めるようになることが“最高の予防”
「怖いから避ける」ではなく、
「知って選ぶ」ことが、子どもの未来を守る最良の方法です。
関連記事(まとめてチェック)
📚 参考文献・出典
- Touvier M et al. Artificial sweeteners and cancer risk. PLoS Medicine, 2022.
- Debras C et al. Artificial sweeteners and cardiovascular disease risk. BMJ, 2023.
- Suez J et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Cell, 2014.
- FFCR(日本食品化学研究振興財団): 食品添加物安全性評価報告, 2000.
- WHO & JECFA: Safety evaluation of certain food additives, 2019–2023 updates.
- 厚生労働省: 食品添加物の指定及び使用基準.

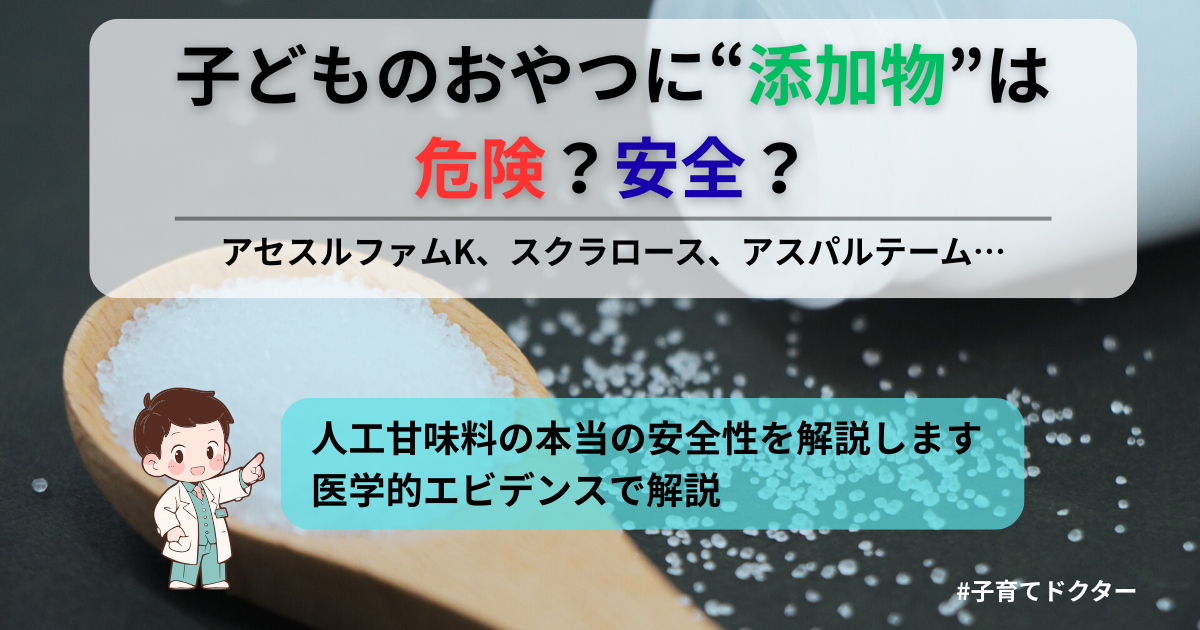



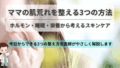
コメント