【医師監修】子どもの熱性けいれん|慌てないための正しい対応・受診の目安と「後遺症・てんかん化・再発」の実データ
医療上の注意:本記事は一般的な医学情報です。けいれんが5分以上続く/繰り返す/強いぐったり/呼吸がおかしい/初めてで不安が強いときは、救急要請や受診をためらわないでください。
迷ったらこちらも:
けいれんを初めて見ると、心臓がきゅっとなるほど不安ですよね。
でも大丈夫。多くの熱性けいれんは短時間でおさまり、後には何も残りません。ここではママ・パパがその場でできる正しい対応と、受診の目安、そして気になる後遺症・てんかん化・再発について、データに基づいてわかりやすく整理します。
熱性けいれんとは?

- 対象年齢:生後6か月〜5歳ごろが中心
- 起こりやすいタイミング:発熱の初期(発熱後数時間以内)
- よくある型:意識がなくなり、全身がびくびくするタイプ(全汎性)
医学的には、発作の特徴から単純型(全身性・15分未満・同一発熱で1回のみ)と、いずれかを外れる複雑型に分けます。
やってはいけない対応(NG)
- 口に物を入れる/こじ開ける:歯の損傷・窒息の危険
- 体を強く押さえつける:けがの原因に
- 冷水や氷をかける:低体温や凍傷のリスク
- 揺さぶる:頭部へのダメージにつながる恐れ
正しい対応(けいれん中〜直後)
- 安全確保:周囲の硬い物をよけ、床やソファに寝かせる
- 気道確保:顔を横向きにして、よだれや嘔吐物を出しやすくする
- 時間を計る:スマホで発作の長さを計測(目安の判断に必須)
- 服のボタンをゆるめる:呼吸を妨げないように
- 発作後:おさまったら呼びかけへの反応、呼吸、顔色を確認
受診・救急車を呼ぶ目安
- 発作が5分以上続く(止まらない/長引く)
- 同じ発熱の中で繰り返す、けいれんが片側だけなど普段と違う
- 発作後もしばらく反応が乏しい・ぐったりが強い
- 呼吸が苦しそう、顔色が悪い、嘔吐を繰り返す
- 初めてのけいれんで不安が強い、持病がある、頭を打っている など
関連:子どもの頭を打ったときの受診目安|CTと被曝リスク / 鼻血の正しい止め方 / 傷は消毒より「洗って守る」
気になる「後遺症・てんかん・再発」
1) 後遺症(発達・認知)
ご安心ください。研究の蓄積では、熱性けいれんの多くは長期的な発達・認知の後遺症を残しません。見た目は激しくても、落ち着けば普段どおりに戻るお子さんがほとんどです。
2) 将来てんかんになる確率
- 単純型:およそ1〜2%(一般小児 ≈0.5%よりは少し高い程度)
- 複雑型:およそ6〜8%
3) 再発の確率
最初の熱性けいれんを経験したお子さんの約1/3(30〜35%)が再発します。初発が18か月未満、発熱から1時間以内の発作、発作時の体温が相対的に低い、家族に熱性けいれん歴がある――といった条件で再発しやすくなります。
4) 「長く続いた」場合(熱性けいれん重積)
5分を超える長いけいれんは救急評価が必須です。画像検査で海馬に炎症・浮腫の所見が出ることがあり、その後いわゆる海馬硬化や側頭葉てんかんへ進む子が一部報告されています。ただし、多くの子は重い後遺症を残さず良好に経過します。
予防・お薬について
- 解熱薬:けいれんの予防効果はありません(不快症状の緩和が目的)
- 抗てんかん薬の定期内服:再発は減らせても副作用が多く、一般には推奨されません
- 頓用(座薬など):ハイリスク例で医師の指示により使うことがあります
まとめ:焦らず、見守る勇気を
熱性けいれんは、見ている親御さんにとって本当に怖いものです。
けれども、そのほとんどは短時間でおさまり、後遺症を残さない一過性の発作です。
- まずは安全を確保し、顔を横向きに
- 時間を計る(5分が目安)
- おさまったら呼吸・反応・顔色を確認
- 不安なときは迷わず受診・相談
医師としてお伝えしたいのは、「焦らないこと」も大切な対応だということ。
あなたの落ち着きが、何よりもお子さんの安心につながります。
今回の記事が、「いざというとき」にあなたの支えになりますように。
ぜひブックマークや保存をしておいてくださいね。











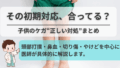

コメント