ADHDかもしれない?――症状の“翻訳”と見分け方・今すぐできる対処・受診準備
この記事は一次ガイドです。最終判断は医療機関で行われます。緊急時は救急受診を。
「頑張っているのに、うまく回らない」。そんな感じが続くとき、背景にADHDの特性があるかもしれません。
ここでは教科書用語ではなく日常の出来事でサインを見つけ、今日から回る小さな一歩を一緒に作ります。
もう少し体系的に学びたい人には、まず一冊の入門書がおすすめです。
基礎を押さえたら、大人のADHD:サインと仕事・家庭の実務対処、
お子さんについては子どものADHD:学校・家庭でのサポートと親の関わり方もどうぞ。
1. ADHD症状を日常に“翻訳”するとこうなる
医学用語の不注意・多動性・衝動性は、決して“性格の弱さ”ではなく、注意の割り振りや行動の切り替え方の傾向です。
いつもの生活の言葉に置き換えると、次のような「困りごと」として現れやすくなります。
不注意 ⇒ 「やり抜けない・抜け漏れる」
- メールを開いても返信し忘れる/下書きのまま
- 説明は理解できるが段取り化でつまずく
- 洗濯→干す→取り込むの連鎖が切れる
多動性 ⇒ 「心と体が落ち着かない」
- 会議中に体を動かす・ペン回し・離席
- 静かな作業が続くと眠気 or ソワソワ
衝動性 ⇒ 「考えるより先に動く」
- 勢いで発言・購入・約束→後悔
- 家族の一言に反射的に言い返す
大人向けの具体例はこちら(場面別サイン)も参照。
2. 5分自己チェック(非診断)
紙とペンを用意して、過去6か月を振り返ってみましょう。これは診断ではなく、受診や対策を考えるきっかけ作りです。
- 先延ばしで締切直前まで始められない(0〜3)
- 物・予定の所在管理ミスが週1回以上(0〜3)
- 会議/授業で意識が飛ぶ・席を立ちたくなる(0〜3)
- 思いつき発言・購入で月1回以上後悔(0〜3)
- 子ども時代にも似た傾向があった(0〜3)
合計8点以上または生活に支障があれば、専門科へ。まずは受診準備を。
3. ADHDっぽいけど別原因かもしれないサイン
似た症状を起こす原因は他にもあります。心当たりが強い項目があれば、一般内科・睡眠科などと並走で進めると安全です。
- 睡眠不足/睡眠時無呼吸:日中眠気・いびき・朝の頭痛
- うつ・不安:興味喪失、身体症状(食欲/体重/動悸)
- 甲状腺・貧血・低血糖:動悸、だるさ、めまい
- 薬や嗜好品:一部抗ヒスタミン薬、過量のカフェイン/アルコール
- ASDなどの併存:対人のズレ、感覚過敏の強さ
4. どのくらい困っていたら受診?判断の目安
「受診のライン」が見えると迷いが減ります。次の4つの視点で冷静にチェックしましょう。
- 頻度:週3日以上の支障(遅刻・締切逸脱等)
- 場面:家庭+職場/学校など複数環境
- 期間:半年以上の持続(子どもは12歳以前の傾向)
- 影響:評価・人間関係・健康に実害
5. 今日からできる対処(仕事/家庭/学業)
コツは「小さく始めて、続ける」。完璧主義より、回る仕組みを作ることを優先します。
- 15分着手→3タスクだけ(紙に手書き→終われば破る)
- 通知の二重化(前日18時+当日1時間前)
- 視覚ノイズの削減(フタ付きボックス化)
- 48時間保留で衝動買いを止める
仕事の実践編は大人のADHD:3週間パッケージへ。
6. 受診準備ワークシート(コピペOK)
初診では「どんな場面で、どれくらい困っているか」が伝わると、話が早いです。以下をそのままコピペしてメモにどうぞ。
【困りごとTOP3】①__ ②__ ③__
【頻度】週__回/【影響】仕事(学校)__ 家庭__ 金銭__
【子ども時代】忘れ物/落ち着きのなさ/成績コメント:__
【睡眠】就床_時・起床_時、いびき/日中眠気:あり・なし
【内科】甲状腺/貧血/低血糖の既往:あり・なし
【服薬・サプリ】__
【希望】環境調整/心理支援/薬物療法の可否を相談したい
7. 関連記事
8. おすすめ本・ツール
9. 参考文献
- CDC. DSM-5/DSM-5-TRに基づくADHD診断項目の概要(英語)。
- NICE Guideline NG87. Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management(2018、更新あり)。
- AAP Clinical Practice Guideline: ADHD in Children and Adolescents(Pediatrics 2019)。
- CADDRA. Canadian ADHD Practice Guidelines 4.1(2020/2021)。
- MSD Manual Professional: ADHD(DSM-5-TR要点)。
- 『注意欠如・多動症-ADHD-の診断・治療ガイドライン 第5版』(じほう, 2022)。






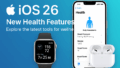

コメント